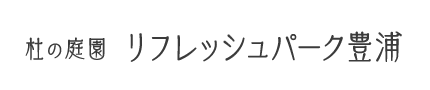庭園長のガーデニング・エトセトラ(30)~日本庭園の源流①~<
日本庭園の原点は、どこにあるのだろうか。
縄文・弥生・古墳時代の状況は、発掘調査等による
考古学的アプローチか、現存遺跡から類推するしかない。
一般的には、6世紀中ごろ、大陸から朝鮮半島経由で
仏教とともに庭園文化も伝えられたと考えられている。
日本書記には、飛鳥時代(612年)に百済から渡来した
土木・造園の専門家、路子工(みちのこたくみ)が、
須弥山(仏教で世界の中心にある山の意)石(噴水装置)や
橋を造形したとの記載がある。
この人物が、記録に残る日本最古の庭園技師だという。
さらに日本書紀には、日本最古の宮廷庭園として、
白錦後苑(しらにしきのみその・飛鳥京跡苑池井関)
の名が記されている。
天武天皇(在位673~686)が祭礼や饗宴を行ったと
考えられており、今後の解明が待たれている。
もうひとつのルーツとして挙げられるのが、
神が降臨する磐座(いわくら)や、神をまつるために
池の中に神島をつくることを庭園のルーツとする説だ。
その源流には、縄文・古墳時代から続く日本古来の
石や自然に対する信仰があると思われる。
近代日本庭園の造園家・重森三玲の孫の重森千靑氏は、
こうした感覚に着目し、「石を立てる」表現として、
環状列石(ストーンサークル)等を例に掲げている。
石に魂が宿るという感覚は、磐座にも通じるものだ。
こうした日本固有の精神的土壌があるからこそ、
大陸から伝わった庭園文化は、単なる模倣にとどまらず、
日本で独自の発展を遂げていくことになり、
庭石、築山、池などが、日本庭園の重要な要素になっていく。
平安時代末期に著された日本最古の造園技術・理論書である
『作庭記』には、こう書かれている。
「ある人曰く、山水をなして、石をたつる事は、
ふかくこころあるべし」と・・・。
庭園長 国司 淑子(くにし としこ)
2026年新春~A HAPPY NEW YEAR ! ~<

あけましておめでとうございます。
リフレの2026年は、和+洋。
日本伝統の松竹梅に、南半球プランツをコーデイネート。
不思議にマッチして、ア ハッピー ニユー イヤー!
園内でも、この寒さにも負けず、昨春に植栽した
さまざまな南半球プランツが、元気に育っています。
3月には、いちはやく春を告げるミモザアカシアの
黄色い花が、咲いてくれるとうれしいのですが・・・。

南半球プランツ・ューイヤー装飾
今年は丙午年。行動力を発揮したり、前進するのが吉。
チャレンジを後押しする年ともいわれています。
リフレも、従来のガーデンスタイルに南半球テイストを
プラスしたり、地域の様々な方たちとのコラボをしたりと、
これまで以上に、外に向かってさまざまな挑戦を
続けていきたいと思っています。
今年も、よろしくお願いいたします。
ビジターセンターでは、2026年のラッキーアクションや
丙午年のトレンド、今年の星座別運試しなどの
パネル展を行っています。ぜひ、お立ち寄りください。
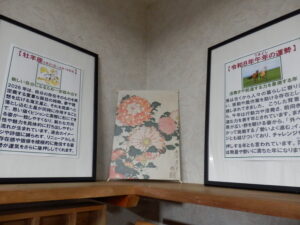
2026星座占いパネル
そして、1年の進むべき方向性のご参考に・・・
スタッフ一同、心よりお待ち申し上げています。

庭園長 国司 淑子(くにし としこ)
旅する蝶・アサギマダラ飛来シーズン到来!!<
アサギマダラという不思議な蝶がいます。
春は、南から北へ。秋は、北から南へ。
移動先で世代を重ねながら、2000㎞もの長距離を旅します。
1日に換算すると、200㎞も移動。すごいエネルギーです。
アサギマダラは、日本で唯一の渡り蝶。この時期だと、
旅の途中、フジバカマの花に集まり、
休息や吸蜜をします。

どうやら、フジバカマの桜餅のような香りが好みのようです。
不思議なのは、フジバカマには、
ピロリジジンアルカロイドという毒が含まれているのに、
アサギマダラのオスが摂取しても、
体に変調をきたさないこと。
それだけでなく、
オスはピロリジジンアルカロイドを取り込み、
フェロモンに変えて、メスを惹きつけるのです。
まさに、魔性の蝶ですね。
なぜ、海を渡っての危険な旅路にチャレンジするのか。
なぜ、まだ見ぬ土地へと命がけの旅を敢行するのか。
正確には解明されていないことだらけなのです。
今季、❝リフレッシュパーク豊浦❞に初渡来したのは、
10月14日のこと。スタッフ一同、その優雅さと美しさと
けなげさに感動!毎年のことですが、
生命の神秘を感じます。
アサギマダラの好む温度は、別名21℃の宝石のとおり、
21℃±5度です。フジバカマも開花温度は15℃~25℃。
必要同士、同じくらいの温度を好むのですね。
そろそろ、涼しくなってきました。
アサギマダラのリフレ帰行のシーズンです。
かつては1日に500頭もの飛来がありましたが、
温暖化の影響か、昨今は頭数が激減しています。
出合えたら、ラッキーだと思ってください。
今日私は、2頭と遭遇しました。それでも感動的!
現在、アサギマダラスタンプラリーも展開中です。
スタンプ2つで、フジバカマの苗をプレゼントします。
奇跡の蝶との、奇跡的な出合いをするために、
お散歩がてら、おでかけになりませんか。
庭園長 国司 淑子(くにし としこ)
10月12㈰~13(月・祝)日、コスモスまつり開催!~晴天・満点・コスモス満開!~<
2025年、おいでませ山口へ~山口県観光サイト~で、
❝豊浦コスモスまつり❞が、コスモス絶景スポットの
第1位にランクされました! パチパチパチ!
毎日新聞、朝日新聞、山口新聞,NHK,KRY等でも
紹介され、2025年の豊浦コスモスまつりは、
猛暑にもかかわらず、おまつりにあわせて満開となり、
連日、たくさんの来園者でにぎわっています。
12日は、夢が丘中学校アサギマダラ蝶査隊の生徒さんたちが、
満開のコスモス苑の前で、旅する蝶、アサギマダラと
フジバカマの花との関係性や生態について、
紙芝居形式で、コスモス鑑賞のみなさんに紹介しました。


生徒さんたちは、この日のために、リフレの庭園長から、
10数回の講義を受け、リハーサルを重ねてきました。
その甲斐あって満開のコスモスの花に囲まれ,発表は大成功!
次は、アサギマダラの飛来調査のための
マーキングの方法を学ぶ予定です。
さて、コスモスまつりは、快晴に恵まれおおにぎわい!
100万本のコスモス景観が、きれいに咲き揃い、
この状態が、10月下旬頃まで続きそうです。
本日13日は、無料音楽フェス❝下関オーガニックビレッジ❞
の2日目も開催されており、佐藤タイジをはじめ、
ベンチマーク、ワンダーヘッズなどが登場。
キッチンカーや露店もにぎやかです。花見台には、
ハロウインのかぼちゃやクレーンカーの空中庭園散歩も登場!

ビジターセンターでは、地元が誇るチェンソーアーテイスト、
安永 多輝さんの、ねんりんピック厚生労働大臣賞受賞記念の
作品展も開催中です。かわいいハシビロコウの作品が目印です。

花見台横のエリアには、❝ネコジャラシックパーク❞の迷路も登場。
中に入ると、いろんなかいじゅうたちのイラストが道案内。
ネコジャラシ迷路も、お楽しみください。

庭園長 国司 淑子(くにし としこ)
10月特別イベント~ねんりんピック厚生労働大臣賞受賞記念!安永多輝チェンソーアート展~<
地元・豊浦町が誇るチェンソーアーテイスト、安永多輝さん。
このたび、「ねんりんピック」最高賞の厚生労働大臣賞を受賞。
地元の新聞等にも、その快挙が大きく取り上げられました。
それを記念して、ビジターセンター内の「杜のアトリエ」で、
受賞後の特別企画「安永多輝作品展」が実現しました。
ビジターセンターの前には、大作「ハシビロコウ」が!
大きなくちばしが特徴で、「動かない鳥」としても有名。
❝松江フォーゲルパ―ク❞で出合い、その愛らしさに魅了され、
等身大の作品に仕上げたそうです。

あまりの愛らしさに、入園者のみなさんに大人気!
スマホで画像を撮り、名前検索したら、
ちゃんと、「ハシビロコウ」と出るほどの精緻さです。
こどもたちは、触って歓声をあげています。
私たちも毎日挨拶して、元気をもらっています。
ビジターセンター内の「杜のアトリエ」には、
その他にも、愛らしい表情の動物たちがいっぱい!

下関市報の9月号に、カラー2ページにわたって特集され、
展覧会を楽しみにしていらしたお客さまがたくさん
観にきてくださっています。
作品展の会期は、10月1日(水)~31日感(金)の1か月間です。
リフレのコスモスも、5~6分咲きになってきました。
10月12日(日)~13日(月・祝)のコスモスまつりには、
満開になる予定です。コスモス散歩がてら、
素敵な作品に出合いにいらしてください。
ファンタジーの世界に引き込まれること間違いありません。
どのこも幸せそうな表情で、観ているだけで癒されます。
一本杉の丸太から、10台のチェンソーを駆使して
彫り出される、チェンソーカーバーの技をご堪能ください。
来年の干支、縁起のいい馬の新作にも出合えます。
庭園長 国司 淑子(くにし としこ)