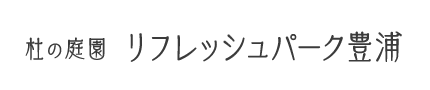山県有朋は、長州藩(現代の山口県)出身で、
明治・大正時代の軍人・政治家。第3・9代内閣総理大臣。
萩の下級藩士の家に生まれ、吉田松陰の松下村塾に学び、
高杉晋作、木戸孝充、伊藤博文らと親交を結ぶ。
後に、高杉晋作の創設した奇兵隊で頭角をあらわし、
第4代司令官として、幕末維新期に活躍。
明治維新後は、新政府より命を受けて欧州視察し、
帰国後、廃藩置県、徴兵制制定、地方自治制度確立、
近代官僚制度などの、新体制構築に深く関わった。
また、文化人としての側面も大きく、和歌をたしなみ、
とりわけ造園築庭には、高い見識と手腕を発揮し、
造園構想の巧みな名手として大きな評価を得ていた。
彼の残した「椿山荘」「無鄰菴」「古稀庵」等は、
近代日本庭園の傑作として広く知られている。
こうした彼の造園へのあくなき探求心と美意識は、
実は、山口のこの地で培われたものだった・・・。
その意味では、我が国の近代庭園のルーツは、
山口の地にあるといっても過言ではないだろう。
さて、山縣有朋は、「無鄰菴」と名づけた邸宅を、
生涯に3つつくっている。
第一無鄰菴は、当地・下関吉田に構えた草庵。
(現・東行庵・・・開基:山縣有朋)
・・・彼は、ふるさと萩の地形や里山風景に
よく似たこの地で、新婚時代を過ごした・・・
「無鄰菴」、それは・・・
「訪問したことを隣家にことづけようにも、
隣家が見当たらないほどの田舎だ」
・・・という意の命名だという。
となりなき 世をかくれ家の うれしきは
月と虫とに あひやとりして 山縣 狂介(後の有朋)
後にこの第一無鄰菴は、高杉晋作(東行)亡きあと
出家した愛人のおうのに贈られ、「東行庵」と名を変え、
ここで、その菩提を弔って一生を終えたという。
第二無鄰菴は、京都の髙瀬川源流に建てられた山縣有朋の別邸。
庭は七代目小川治平により改修されている。
現在は、豆腐料理の名店『がんこ髙瀬川二条苑』として、
旅行客の人気を集めている。
第三無鄰菴は、京都南禅寺あたり・・・。
明治24(1891)年、小川治兵衛に指示し造営。
東山を借景とし、琵琶湖疎水の水を取り入れて、
小さな瀑布、流れ、石橋を配し、30本の樅の木などの樹木、
そしてイギリスの自然風景式庭園に影響された芝生を導入した。
「従来の人は重に池をこしらえたが、自分はそれより
川の方が趣致がある」
『苔によっては面白くないから、私は断じて芝を栽る」
「この庭園の主山(しゃっけいというはのう、
此前に青く聳える東山である」
無鄰菴は、すべて東山を軸にして造営されている。
そして、自然主義の作庭理念のもと、1000坪の敷地に、
従来の日本庭園とは一線を画し、芝生はもとより、
里山風景から深山渓谷の風情までをも取り入れている。
それらは、山口県人にはどこか懐かしく、心安らぎ、
ふるさと山口の見慣れた里山景観を髣髴とさせる・・・
明治40年の『続江湖快心録』には、こう記されている。
〇苔のかわりに芝生を張る。
〇瀑布の岩石の間に羊歯を植える。
〇京都の庭木にはあまり使われなかった樅の木を植える
〇水が滞留する池ではなく流れをつくる。
「以後の庭園はことごとく無鄰菴に倣っている」と。
「無鄰菴」に加え、東京の「椿山荘」、小田原の「古稀庵」
は、「山縣三庭園}と称されるが、椿山荘の碑には、
「後にここに住む人もこの自然を守り続け、
この山水を楽しむような私の望み通りの人物であろうか」
と記されている。
庭を見れば、心はいつでもふるさと山口の野山に
戻ることができる・・・
近代日本庭園の原風景は、ここ山口にある。
日本の庭園維新も、山口を発祥とするということである。
庭園長 国司 淑子(くにし としこ)