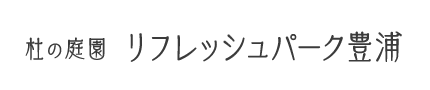現在、NHKで放映されている大河ドラマ「べらぼう」。
江戸時代中期に出版社を興し、江戸の文化を築いた
人物のひとり、蔦屋重三郎を主人公にしている。
喜多川歌麿、葛飾北斎、東洲斎写楽、曲亭馬琴、
十返舎一九などを世に送り出した名プロデユーサーだ。
大河ドラマは史実をベースにしたフィクションなので、
江戸時代の暮らしや文化を知る意味でも興味深い。
出版業が隆盛を極めたということは、泰平の世が続き、
暮らしが安定し、人々の識字率も高かったということ。
当時の江戸は、100万人という世界一の人口を擁し、
識字率も世界一。園芸文化も花開いていった・・・
改めて、日本人のポテンシャルはすごいのだと思う。
蔦屋重三郎は、こうした庶民の花卉園芸熱に着目し、
生け花図を並べた画本、『一目千本』を出版した。
「花」と「遊女」を重ね合わせる趣向が受け入れられ、
「一目で千本の花が視界に入る風趣」が人気を博した。
ガーデニング的な視点でいうと、
この時期、将軍・大名の庭園づくりから庶民の園芸熱に
至るまで、日本人の植物愛は、世界に類を見ない高まりだった。
染井村には植木屋や苗木園が集積し、世界最大規模を誇っていた。
植木鉢の本格的な普及も、このころのことだ。
さらに、庭見せ、花見、花を巡る旅なども流行した。
江戸は、世界初・世界一のガーデンシテイだったといえる。
幕末期に江戸を訪れたイギリスの植物学者、
ロバート・フォーチュンは、下記のように語っている。
「郊外のこじんまりした住居や農家や小屋の傍らを
通り過ぎると、家の前に日本人好みの草花を少しばかり
植え混んだ小庭をつくっている。日本人の国民性の
いちじるしい特色は、下層階級でもみな生来の
花好きであるということだ。気晴らしにしじゅう
好きな植物を少し育てて、無上の楽しみにしている。
もしも花を愛する国民性が、人間の文化生活の高さを
証明するものとすれば、日本の低い層の人々は、
イギリスの〃階級の人たちに比べると、
ずっと優れてみえる」
蔦屋重三郎が出版した浮世絵や錦絵のなかにも、
さまざまな草花や園芸に関わる情景が登場する。
ガーデニング的な視点で、江戸時代の園芸熱を
ひもといてみるのも面白うと思う。
庭園長 国司 淑子(くにし としこ)